
(7) 門松は冥土の旅の一里塚 門松は冥土の旅の一里塚 ・・・・・・ 年々、一休の詠んだこの歌が感覚にフィットするようになってきた。それにこのシニカルさ、たまらないではないか。まさに下の句の、めでたくもありめでたくもなし、なのだが、私としてはどちらかと言えば、めでたくもなし、の方だ。 時間の経過を早く感じる度合いは、年齢に比例するという説もある。それには多少異論を唱えたいが、もしそうだとすれば、現在私は時速64キロメートルで疾走中といったところか。あと半年もすれば65キロメートルに加速だ。門松など、一瞬で車窓から遠ざかる電柱のようなものだろう。振り返ると小さく束になって遠くに見えるというか ・・・・ いったいどこまで加速するのか。いや、ひょっとすると電池切れでゆったりと止まるかもしれない。いずれにしても急停車だけはしたくないものだ。好きな酒をもっと長く味わいたいとも思うし。 ところで昨年の暮れ、急な依頼ではあったが、十和田の市立中央病院というところで弾いてきた。病院という場所での演奏は初めてだったが、広い吹き抜けのロビーは響きもよく、なかなかしゃれたサロンといった風であった。冷たい雨の夜という事もあり、聴衆は100名程度だったが、青森から駆けつけてくれたラジオのパーソナリティーをやっている友人の飛び入りの司会もあって、久しぶりに弾いていて楽しめる会であった。聴衆の反応は ・・・・・ ? 私が演奏したのだからまちがいないではないか! 確か、コルトーの来日は1952年、つまり昭和27年のことだ。すでにひどく衰えて、よぼよぼであったはずだが、私の知る限りでは、山口の宇部から東北まで、移動するだけでも困難な時代に、精力的に演奏を行った。今のように音楽が溢れている(決して本物ばかりではない)現代と違って、敗戦後まもない日本のことでもあり、どれほど新鮮に心に響いたか想像に難くない。私にとっても演奏というものを考えさせられる時間であったし、最近かなりシニカルな心境になっている自分にとっても演奏する意欲をかきたてられたことであった。 ・・・・・ という訳で、東京での演奏会を開いてほしいという声もあり、私としてはいつでもご期待に添いたいのだけれども、何せ、需要と供給のバランスはもとより、場所やホールの諸条件もあり、なかなか思うに任せないのですよ。 これが一番のネックなのだが、まあ、酒でも飲んでゆっくりと考えますよ。 とりあえず、皆さん、おめでとう。世間がそう言っているので。 Jan. 1, 2013 またまた年が明けてしまった。年々時の経過に加速度が付き、一体今年が平成何年で西暦何年なのか、とっさにはようわからん。人生もっとゆったりと各駅停車で行きたいと思うんだが ・・・・。 いや、すっかりご無沙汰してしまった。皆様いかがお過ごしだろうか。 私はと言えば、昨年来体調が芳しくなく、心身ともに絶不調といった状態で往生している。歳のせいもあるとは思うが、5月の演奏会以降、目立ってガタが来た。今思えば、あの震災直後のこの国を覆う異様な状況の中、頻繁に揺れる楽器を前にさらい続けることは、かつてないほどの苦行であった。そのストレスのせいでもないだろうが、6月には腎臓結石で生れてはじめて救急車の世話になった。まあ、命にかかわるようなものでもないが、あの息がとまるほどの強烈な痛みは、この歳にして改めて生き方を考え直すに充分であった。本当に、人間いつ何時何が起こるか分からないものだ。 皆様も健康に留意して良い1年を。
ごまかすのも芸の内、という言葉がある。ごまかすというと何やら後ろめたい響きがするが、演奏中に破綻をきたした場合、その場をいかに取りつくろうかは、演奏する者にとって大きな問題だ。商品化されたレコードやCDなどではありえないが、ライブ演奏においては、凡人ならいざ知らず、名人大家といわれる人であっても、常に起こり得る事態でもある。破綻といってもピンキリで、一つや二つ音を外したくらいではそのうちに入らない。もっとも最初から終わりまで外しっ放しというのもあるんだが・・ここでは論外だ。ここでいう破綻とは、一瞬記憶が飛んでしまう、つまり、ここはどこだ? という状態に陥ることだ。幸い私は今までそのような経験はないが、聴いた限りではかなりの数にのぼる。その度に、人ごとながら凍りつくような思いをしたものだ。本人の資質にもよるんだろうが、山手線よろしく廻り続け出口の見えない者、引き込み線に入ってしまい立ち往生する者、溺れかかってバタバタとのたうち回った挙句、ついに沈んでしまう者、色々だ。そういえば、シューベルトの「さすらい人幻想曲」で本当にさすらってしまい、止まって鼻をかんだすごい人もいた。いやはやあっぱれというか ・・ しかしこれらは大方、はなから破たんの予測がつく人たちであって、そうたいした問題ではない。 名人大家といえば、あのルビンシュタイン (Artur Rubinstein) にでさえアクシデントは起こるのだ。1968年の日本公演で、モーツァルトのコンチェルト K466 を演奏中、終楽章で突然迷い道に入ってしまった。どうなるかと固唾をのんで見守っていたのだが、しばらくさ迷った後、さりげなく元の道に戻ってしまった。その間、彼は全く慌てる風でもない。むしろ、うろたえたのは指揮者の方だったろう。アンコールで弾かれた彼の十八番であるはずのショパンのポロネーズ Op.53 「英雄」でも同じことが起きたのだが、同様に全く意に介さぬといった表情で乗り切ってしまった。その堂々たる様は、たまたまかすり傷を負った程度のライオンのようであって、少しも彼の音楽や名声を傷つけるものでなかったことは確かだ。これはもう立派な芸というほかはない。 伝え聞く話ではあるが、あのアルフレッド・コルトー (Alfred Cortot) は、時々演奏中にド忘れを起こし、譜面を見に楽屋に戻ることがあったそうだ。信憑性はともかく、これには、演奏会の翌日は決まって、「夕べのおやじの演奏は無事だったか?」といった挨拶代わりの会話が、学生たちで交わされた、という尾ひれまでついている。多少眉唾だが、もし事実であるならば、ホッとする話ではないか。聴衆がそれを許容し楽しむことが出来たならば、楽屋に戻る姿さえも絵になるかもしれない。今日のような硬直して儀式化してしまった演奏会では考えられないことだが、当時、彼のような演奏スタイルなら可能だったかもしれない。私としては、また、その彼の演奏スタイルからして、ド忘れ事件は起こりえたと思っているのだ。 破綻を真に名人芸的技を持って取り繕う事は、いかに演奏力に長けた人であっても、そう簡単なことではない。演奏力だけでなく、即興および作曲、編曲の能力が必要不可欠だからだ。リストは弾き間違えた音をもとに自在に転調を楽しんだと言うし、ラフマニノフはポリフォニックな即興演奏に長けていたとも言われる。だが、作曲と演奏が分業化してしまった今日、そういった話はもはや伝説になってしまっている。
追伸 Dec. 26, 2010 (4) ビールにまつわる神聖なる儀式 今年の夏はひときわ長く過酷であった。 元来夏好きの私ではあるが、この執拗で暴力的ともいえる暑さには、さすがに参った。 外に出る気力もなく、避暑地へと赴く身分でもないので、日がな一日冷房が効いた部屋で過ごし、ひたすら夜はビールを楽しむという毎日であった。そのためか、体重は今までの最高値を記録してしまい、気がつけばほとんどのズボンが入らない有様である。これはゆゆしき事態、まさに緊急非常事態である。立派に育ってしまったビール腹? を眺めつつ、なんとかせねばならん と焦るのだが、好きなビールをやめるのは辛い。だがしかし、これはあながちビールだけのせいでもあるまい。要するに怠惰な生活のつけが回ったためであり、従ってビールに罪はないのだ。これからの空気が乾燥する季節は、ますますビールが旨くなる。飲まない手はないのだ。 ・・・・ と言い訳がましく考えたりもしている。 ところでそのビールだが、ビールのみならずアルコール類を“命の水”ならぬ“神の水”と思っている私には、飲むにあたっての特別な儀式のようなものが存在する。まあ、多かれ少なかれ酒好きには飲み方のこだわりがあるだろうが、私の流儀は稀であろう。それはズバリ、歯磨きである。そんなことをしたら味覚が麻痺するだけではないのか、と拍子抜けする御仁もあろうが、いやいやご心配なく。磨き粉は一切つけずにブラシだけで磨く。最低でも15分程度は時間をかけて丁寧に磨くのだ。もちろん舌の汚れも落とし、歯の間もデンタルフロスできちんと清掃する。これをするだけで味覚が敏感になり、酒の味は格段に違う。かなり面倒と思われるだろうが、私に言わせれば、旨いものをより旨く味わうため、大げさに言えば、尊いものを受け入れるための当然の儀式なのだ。大事な客を迎える際、普通は部屋の掃除くらいするではないか。 私の場合、アルコールタイム及び食事は、通常入浴後と決めている。風呂から出た後は、いわゆる旨く飲むための作法である。まずおもむろにビールとグラスを用意する。この際つまみは一切要らない。ビールは何日も冷蔵庫に眠っているものは当然ダメで、飲む5〜6時間前から冷やしてあるものに限る。出来れば瓶ビールに越したことはないが、冷蔵庫のスペース上文句は言えない。グラスにしても、汚れや油分の付着したものはもってのほかである。他の食器類とは分けて洗い、拭かずに自然乾燥させた専用のものがベスト。グラスの形状は,妙なくびれ等ないストレートなタイプが私の好みだ。ジョッキのような厚みのあるものは野暮ったくて旨さを損なう。かと言って過度に薄いいわゆる高級品のようなものは口当たりが不安定で、慌てて飲むと歯でガラスを割りそうで危険だ。ウイスキーのロックグラスとはわけが違うのだ。グラスの大きさとしては500ミリリットル缶を二度で注ぎ終えるくらいのものが最適であろうか。 さてここから、はやる喉に“待て“をかけてビールを注ぐわけだが、慌ててはいけない。作法はゆっくりが良いのだ。言わずもがなのことだが、ビールを味わう決め手は、何と言ってもきめ細かでクリーミーな泡だ。すぐ消えてしまうような粗い泡では台無しだ。理想的な泡を立てる条件は温度にある。必要以上に冷やすと泡立ちも悪く、ビール本来の味も失せる。キンキンに冷やして飲むという人もいるが、私にはまったく理解できないところだ。泡と液体の比率は 7 対 3 、8 対 2 と好みもあろうが、私はややこだわって、7.5 対 2.5 といったところか。このくらいが見た目にも旨そうに感じる。注ぎ方や泡の立て方は各々あると思うが、私のやり方としては、グラスを置いてまず最初にやや勢いよく半分近くまで注ぎ、基本になる泡の量を確保する。しばらく待って上の粗い泡がおさまった後、グラスを手にとって丁寧に注ぎ足していく。その際、グラスを斜めに傾けるかどうかは臨機応変で、要は理想の比率を作るための勘を働かせればよいのだ。途中無理やり泡立てたり、注ぐのを中断するのはやめた方が良い。あくまでも流れるような作業に終始することが大切だ。泡が上の方まで来たら、一度グラスを置いて泡を安定させる。その後少し注ぎ足して、泡がグラスの上にやや盛り上がった状態で完成だ。この時理想的な比率になっていれば上出来である。ここで初めて、待て! お預け! から よし!になるわけだが、くれぐれも豪快に飲み干してやろうなどと勘違いしてはならない。相手は清涼飲料水などではない。黄金色の液体を、泡の底からすくうように飲むのだ。さすればトロリとした味わいと共に、古来からの人類の偉大な知恵を感じ、最初の一杯のほとんどが税金であることさえも忘れることが出来る。グラスを干した後、鼻の下に白い泡の髭が残れば完璧だ。 どんな飲み方だろうが、人の勝手ではないかとの声も聞こえてきそうだが、騙されたと思って、一度歯磨きからやってみてくだされ。銘柄云々など枝葉末節。いや逆に、よりはっきりするかもしれんデス。
最後に、究極の飲み方を書いておく。それは夏の夜、1時間ほど全力で歩き回った後、風呂に浸かって飲むビールである。まさに命の水を実感できること請け合いである。かなりリスキーだが、興味のある方は来年の夏あたりやってみてくれ。私は ・・・・ ? 危ないので今はもうやらない。
追伸 Sep. 26, 2010 (3) ハンガリア狂詩曲 - 未発表の音源から 梅雨まっただ中である。だからという訳でもないが、今回はそのうっとうしさを払拭する意味も含め、リストの「ハンガリア狂詩曲」の2番をお聴きいただこうと思う。もちろん演奏は私で、もちろん!ライブである。かなり若い頃のものであるため、今となっては気に入らない点が多々あるのは否めないのだが、まあ、それはそれである。たとえ昨日行ったものであれ、今日は気に入らない点がいくつも生じるのが演奏というものだから、これはこれでいいのだ。ライブならではのスリルをお楽しみくだされ。 ところで、この「ハンガリアの2番」と言えば、この曲を聴いたことがない、という人間がいないくらい、よく知れ渡った名曲だ。SPレコード時代からオーケストラを含め、数多くの演奏者の手にかかってきた。しかし今現在からみれば、それらの多くは大げさで、悪く言えば芝居がかった表現に終始する、いわゆる“前時代的”スタイルでもあったのだ。あるべき姿からは程遠いイメージが定着してしまったともいえる。 ところが半世紀余り前、ある演奏家の出現により、ドラスティックにそのイメージが変わったのだ。その唖然とするほど見事でタイトな演奏は、かのH.C.ショーンバーグをして「ここにはじめて、リストの狂詩曲の、真にイディオマティックな演奏をなし得るピアニストが出現した」と言わしめた。この演奏により、はじめてリストの狂詩曲(2番だけではない)は、本来の光を放ったとも言える。事実この演奏に出会った時、まだ私は子供だったが、心底驚愕したのを覚えている。今にして思えば、この出会いこそがおそらく私の生涯にわたって、この演奏者が最も魅力的な存在であり続けることの始まりだったのだ。だが、ここではあえてその名前は伏せておこう。知っている人は知っていますよね。彼のことはまた別の機会に述べたいと思う。
Jun. 26, 2010 (2) デジカメ侵略者論 そんな訳で、長年にわたる私のゆる〜い趣味であったアナログカメラなんぞ、あっという間にデジカメとやらに駆逐されてしまい、今では一部で、銀塩カメラ等といったおそろしく前時代的呼び名で区別される有様だ。暴落した値札をつけて中古店に並ぶその姿は、さながら、成仏できない亡者の群れ、といったところか・・・・。 寂しいというか虚しいというか、いや、これも時代なのだ、などと妙に納得する半面、いとも簡単に、世界に冠たる精密機械工業の技術を捨て去る在り方に怒りも沸いてくる。
(1) 寅年を機に少しは吠えてみようかと ・・・ 幼い頃から、音楽は私にとって絶対的な存在であった。言葉や文字を超越したところにあるのが音楽であり、私の場合、演奏することによって全てを語ればよいと思ってきた。かなりの思い込みと取られるかもしれないが、この考えは今でも基本的に変わらない。曖昧な言葉や文をもって(こちらの方が私にとっては曖昧かつ抽象的だ)余計なことを言うくらいなら、むしろ黙ってその絶対的なものの中に身を置いている方が、はるかに楽である。今日のような社会にあっては尚更で、そもそも言葉や文というものは、それが公になった途端、過激な演奏などよりもずっと危ない。言わぬが花の例えもあるのであって、だからこの先も、私が文を書くことなど一切ないと決め込んでいたのだが、どういう訳か最近になって、やや考えが変わってきた。頑なさが崩壊しつつあるのだ。 常々、私の話は面白い、と言ってくれる何人かの知人や、出版業を営む友人からの「思う事を書いて本にしてみたら?」等といった殆どおだてともいえる薦めもあり、数年がかりの重い腰をあげてみようか…とも思い始めたのだ。 とは言うものの、文を書くという作業は、やはり私にとってはかなり難儀で、演奏以上に用意のいることだ。作文少年の異名をとった子供の頃の文才?も、とうの昔に消え失せてしまった。漫画ばかりを読んだためだと人は言うのだが、それだけでもあるまい。 自分で言うのも面映ゆいのだが、私はどちらかと言うと雄弁な方だと思っている。酒など入ると、更に、それに拍車がかかるのであって、聞く羽目になる家内などは、多少閉口しているかもしれないが、人とは異なる視点が非常に面白いとも言う。だがそれを文に起こすとなると、事は別である。所詮喋りは、無責任と言えるほど、瞬時に消えて行くものだから。
ひょっとしたら作文少年に戻れるのでは … という微かな期待も私にはあるのだ。 目を通していただければ幸いだ。 Jan. 8, 2010 あえてアナログ思考 |
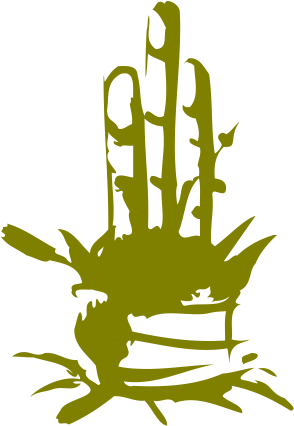



 と、まあ、四の五の言ったところで、所詮は文章力欠如の自己弁護にすぎないのだが、60を過ぎた今、私としては、多少なりとも、虎の毛皮ならぬ自身の毛皮?を残したいと考えだしたのだ。「言った者勝ち」という友人の助言を受け入れて、折に触れ、戯れごと等綴って見ようと思っているのだ。
と、まあ、四の五の言ったところで、所詮は文章力欠如の自己弁護にすぎないのだが、60を過ぎた今、私としては、多少なりとも、虎の毛皮ならぬ自身の毛皮?を残したいと考えだしたのだ。「言った者勝ち」という友人の助言を受け入れて、折に触れ、戯れごと等綴って見ようと思っているのだ。
